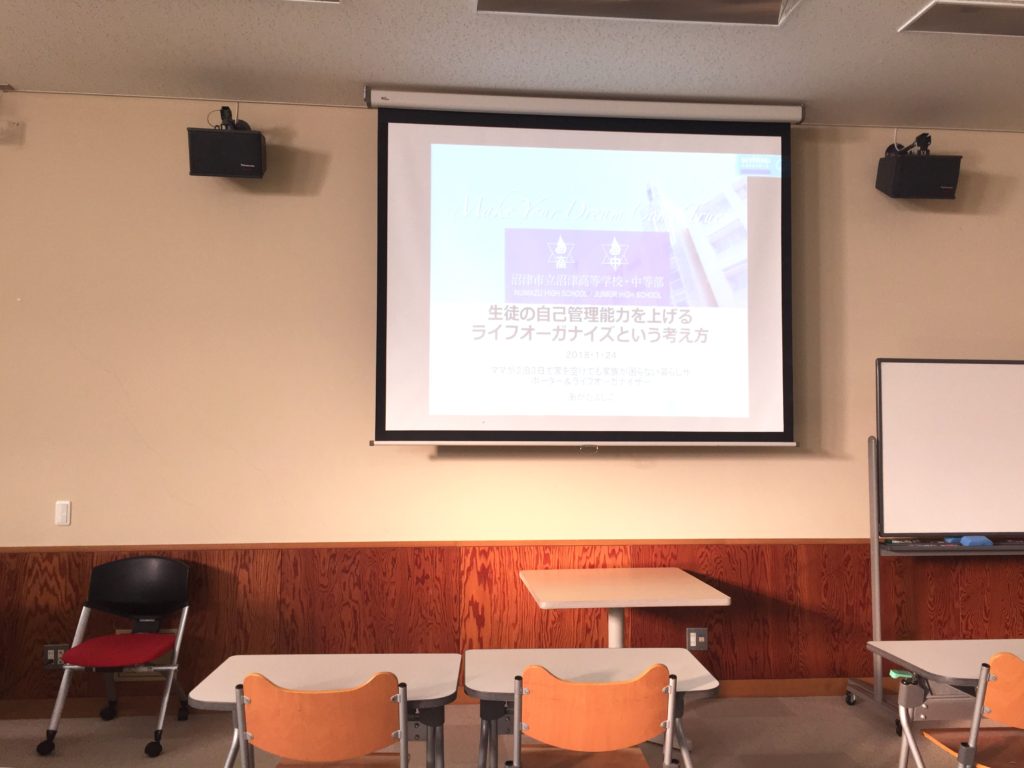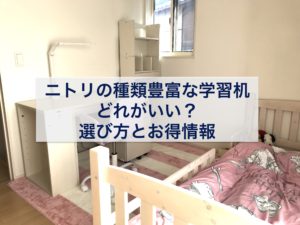全国的にも、我が子の通う学校でも学級閉鎖が相次ぐ中、インフルエンザの脅威にも負けず、沼津市立沼津高等学校・中等部の教員向けに
「生徒の自己管理能力を上げるライフオーガナイズという考え方」というタイトルで講演をさせていただきました。
開催に至った経緯
経緯については、こちらの記事で詳しく書きました。
先生方はどんなお悩みを持っている?
冒頭に、現状のお悩みを書き出していただくワークを取り入れました。
先生のお悩み・・
生徒の中には学習用品をはじめとした自分の持ち物をきちんと管理できない
結果、プリント類の紛失や忘れ物などが起きたり
部室や道具の整理整頓が行き渡らない
そんなお声が挙がりました
生徒に対して、と同等に、もしくはそれ以上に先生自身の、「書類」管理に関するお悩みも多いようでした。
お伝えしたこと
そんな先生方に対して、
自己管理能力を上げるために、まず、目に見えるものを片付けることは有益であること。
そのためのスキル、これはもののかたづけ方というよりは、
生徒たちが、「やってみようか」と思えるように導く思考の整理
をぜひ身につけていただきたい。
これらを
1 ”片づけよう”を阻む要因
2 ライフオーガナイズとは
3 実際のシーンでのオーガナイズの活用
の3つの構成にまとめ、その具体的な思考の整理の方法をお伝えしました
どんな結果や効果をお持ち帰りいただけたか
先生方は、お互いの考えをシェアしあうのがとても上手なのですね。
シェアの時間がとっても盛り上がります。
一通り話をさせていただいた後、ご自身が冒頭にあげたお悩みを、どう解決したらいいと思うのか、改めてお隣どうしでシェアしてもらいました。
そこから聞こえたお声は、
「多くの時間を過ごす 教室・机・ロッカー・部室
生活環境は気持ちのいい場所かどうか?
生徒にまずは聞いてみて、どう改善していくのがいいのか、どういう方法なら気持ちいい、好きを維持していけるのか、話し合ってみたい。」
「子どもが提出書類をうまく管理できないことについても、3色くらいのカラークリアファイルなどを使って、
◯色は親に必ず提出、▽色は自分で保管、
などわかりやすくしてあげることで、紛失しにくく、探しやすくなるのでは?と長年の懸案が解決される気がする。
実践してみたい」
そんなお声をいただきました。
など、具体的な行動を伴そうな結果を導きだすことができ、よかったなと思っています^^
結論
情報もモノも10年前と比べて格段に溢れている現代において、片づけのスキルは、”なんとなく”や”自己流”では通用しませんし、先生方がそこに苦労し時間をかけることも、他に多大なやるべきことがある中で、違うんだろうなぁと、片づけのプロとしても、一保護者としても思います。
ですから、教員・生徒・保護者に向け、必要な情報をわかりやすく提供していくことは、子どもが過ごす生活環境をよりよくしていくことに繋がるのだと思います。
これは、学校だけでなく、会社にとっても同じです。
片づけは、環境を綺麗にするための目的ではなく、より効率を上げる、コミュニケーションなどを円滑にする、結果として業績を上げる、などのための手段なのですから^^。